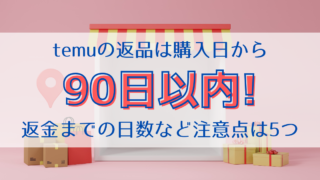 お役立ち情報
お役立ち情報 temuの返品は購入日から90日以内!返金までの日数など注意点は5つ
temuは購入日から90日以内であれば、条件を満たした商品を返品・返金できます! temuの商品は安くてついついたくさん買ってしまい、後から「これ買わなくても良かったなあ。」と後悔することもありますよね。 実際に届いた商品が、写真よりも安っ...
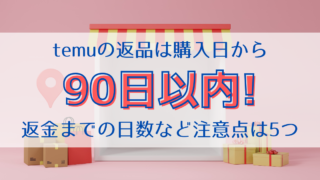 お役立ち情報
お役立ち情報  お役立ち情報
お役立ち情報 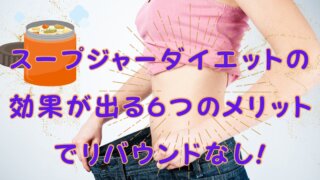 お役立ち情報
お役立ち情報  お役立ち情報
お役立ち情報  お役立ち情報
お役立ち情報 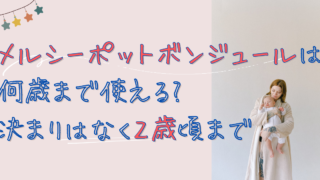 お役立ち情報
お役立ち情報  お役立ち情報
お役立ち情報 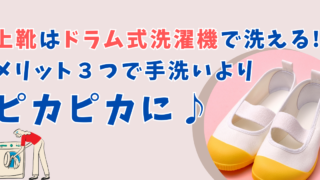 お役立ち情報
お役立ち情報 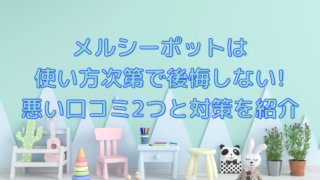 お役立ち情報
お役立ち情報 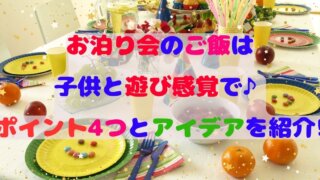 お役立ち情報
お役立ち情報