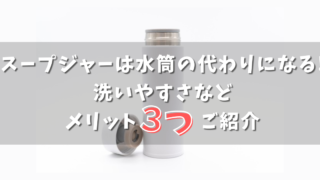 お役立ち情報
お役立ち情報 スープジャーは水筒の代わりになる!洗いやすさなどメリット3つご紹介
水筒の代わりにスープジャーを使うと、洗いやすさやマグカップに似た安定感があるなどメリットが3つありますよ♪ スープジャーと水筒は似ているので、「スープジャーは水筒の代わりになるのでは?」と思いますよね。 スープジャーと水筒は見た目が違うだけ...
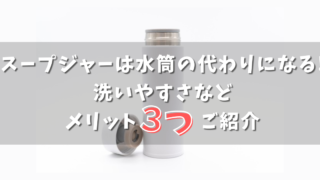 お役立ち情報
お役立ち情報 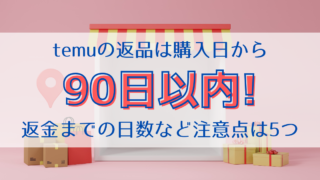 お役立ち情報
お役立ち情報  お役立ち情報
お役立ち情報 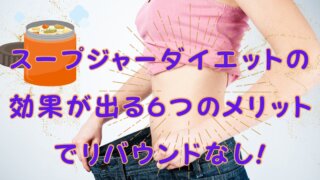 お役立ち情報
お役立ち情報  お役立ち情報
お役立ち情報  お役立ち情報
お役立ち情報 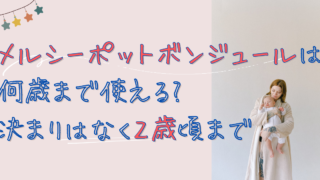 お役立ち情報
お役立ち情報  お役立ち情報
お役立ち情報 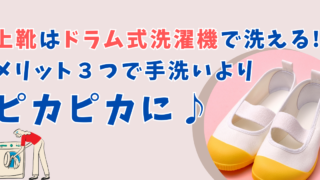 お役立ち情報
お役立ち情報 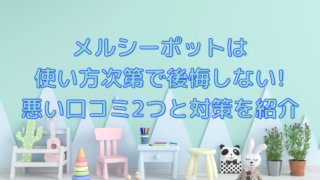 お役立ち情報
お役立ち情報